
人手不足、労働環境の変化、そしてAIの進化。これらが同時に進行する今、私たちの暮らしや働き方を支える「サービスロボット」が次々と社会へ浸透しています。
物流や小売、接客、医療、そして教育まで——ロボットは“人の代わり”ではなく、“人と共に働くパートナー”として新しい社会のかたちを作り始めています。
サービスロボティクスとは?──人と共に働くロボットの時代へ
これまでロボットといえば、工場で正確に動く「産業用ロボット」を思い浮かべる人が多かったかもしれません。
しかし今注目されているのは、家庭やオフィス、店舗など「人が生活する空間」で共に動くサービスロボットです。
調査によると、国内のサービスロボット市場は2025年に約6,000億円、2034年には2兆円を超えると予測されています。背景には、AIによる環境認識や自律制御、クラウド通信などの技術革新があり、これまで人にしかできなかった接客・配送・監視・案内といった業務の一部をロボットが担う時代が現実化しているのです。
では、どのような企業がこの潮流をリードしているのでしょうか。本記事では、NewVentureVoiceが過去に紹介した中から、国内外で注目される以下の4社を紹介していきます。
- Telexistence――世界に存在するすべての物体を、ロボットで動かす
- 株式会社Mujin――ロボットに“考える力”を与える。
- Cartken――街を走る、もう一人の配達員
- avatarin株式会社――“行く”を超える、新しい移動のかたち
社会を変える!注目のサービスロボット企業4選
Telexistence――世界に存在するすべての物体を、ロボットで動かす

Telexistence株式会社(テレイグジスタンス)は、コンビニエンスストアや倉庫などの現場で、遠隔操作とAI自動化を組み合わせたロボット「TX SCARA」を展開しています。
こちらはローソンやファミリーマートで実際に導入されており、飲料補充を自動化することで夜間帯の人手不足を補っています。
最大の特徴は、人工知能による自動制御と人力での遠隔操作技術を組み合わせている点です。これにより、小売店舗内での商品陳列業務をロボットで代替する。店舗立地に制約されない労働参加や採用、運営コスト削減を実現しています。
2023年にはソフトバンク、Foxconn、KDDIなどから総額230億円を調達し、米国や東南アジアにも進出し、“人とロボットが協働する店舗”という新しい働き方を提案しています。
個別記事はこちらから
株式会社Mujin――ロボットに“考える力”を与える
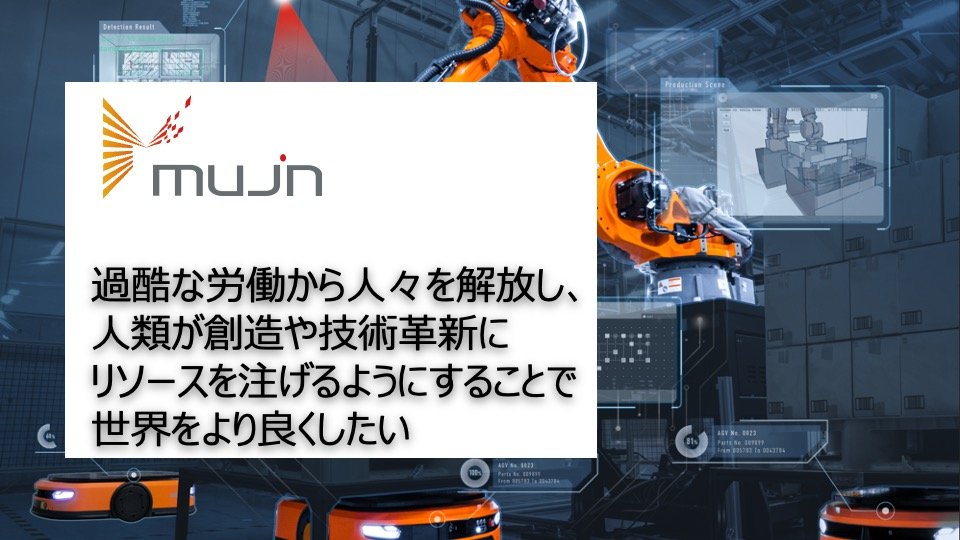
株式会社Mujinは、「人が教えなくても動けるロボット」を目指し、知能ロボットの開発・販売を行っています。物流倉庫でのピッキングや仕分け、パレット積みといった作業を自動化し、Amazonやユニクロなど国内外の大手企業に導入されています。
Mujinの強みは、独自の高度なロボット知能化技術「MujinMI」によりこれまで不可能であった物流・製造現場の自動化を実現している点です。この技術を搭載して構成機器を多数開発しており、今まさに日本発のロボティクス産業を牽引する存在となっています。
個別記事はこちらから
Cartken――街を走る、もう一人の配達員

Cartken(カートケン)は、自律走行デリバリーロボットで注目を集めている、米国カリフォルニア発のスタートアップです。
AIカメラとセンサーを搭載した小型ロボットが、歩道を安全に走行し、食品や小荷物を届ける仕組みで、すでにUber Eats Japanや三菱電機との提携を通じて、日本でも実証運用が進んでいます。
Cartkenの強みは、高度なAIモデル・アルゴリズムを活用した物体検知技術や自律走行性能を兼ね備えている点です。「カメラを通じて取得する映像には個人を特定できないようマスク処理を行う」など、通行人のプライバシーにも配慮しているのも大きな特徴です。2024年には約14億円を調達し、米国・日本・欧州で展開を拡大中です。
個別記事はこちらから
avatarin株式会社――“行く”を超える、新しい移動のかたち

avatarin株式会社(アバターイン)は、ANAホールディングス発のスタートアップで、「移動の民主化~すべての人が持続的にいつでも、どこへでも自由に移動できるように」というミッションを掲げており、アバターロボット「newme(ニューミー)」を開発しています。
こちらは、遠隔地を自由に動きまわり、ディスプレイにスタッフの顔を表示して対面での会話が可能な接客・案内に最適なアバターロボットです。遠隔でも接客、案内業務を提供することができ、人材が不足している幅広い業界にソリューション・サービスの提供を可能にします。
同社は、2024年にはシリーズBで約37億円を調達し、累計資金調達額は77億円に到達。“移動の民主化”を掲げ、教育・医療・観光など、人が「行くこと」に価値を見出す分野で新たな社会基盤を築こうとしています。
個別記事はこちらから
ロボットがもたらす新しい社会像
これらの事例から見えてくるのは、ロボットが人の仕事を奪う存在ではなく、人の可能性を拡張する存在へと変化しているということです。
近年では「Robot as a Service(RaaS)」と呼ばれる月額利用型モデルが広まり、中小企業や自治体でも導入が進んでいます。
AI技術との融合により、ロボットは“命令を実行する機械”から“自ら判断し共に働く仲間”へ。
清掃、接客、警備、物流といったあらゆる現場で、ロボットが当たり前に働く時代はすぐそこまで来ています。
まとめ──“ロボットが当たり前にいる世界”へ
サービスロボティクスの進化は、単に効率化を進めるだけではありません。それは、「働くとは何か」「人ができることは何か」という問いに対する新しい答えでもあります。
ロボットはすでに実証実験の段階を超え、社会の一部として定着しつつあります。ロボットが隣で働く未来は、もう“未来の話”ではありません。人とロボットが協力しながら暮らす「新しい日常」として、静かに始まっているのです。
New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。
国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もご覧ください。







