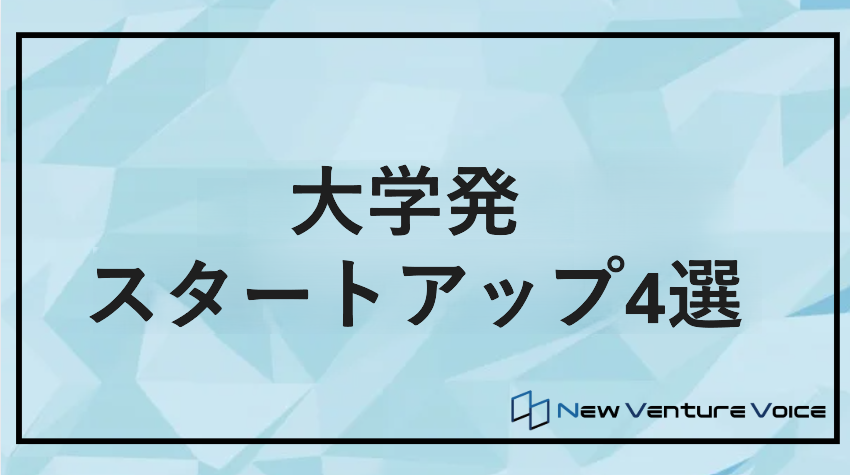
大学発スタートアップとは、大学の研究成果を基に設立されたスタートアップ企業のことです。近年、このような大学発の企業が日本で急増しており、産学連携によるイノベーション創出に大きな期待が寄せられています。実際、経済産業省の調査では2023年時点の大学発スタートアップ(大学発ベンチャー)数が4,288社に達し、前年から500社以上も増加して過去最高を記録しました。大学で生まれた先端技術や知見を活かし、医療・環境・エネルギーなどの分野で社会的課題に挑む企業が次々と登場しており、投資家からも注目が集まっています。
今回は、その中から大学発スタートアップの注目企業4社を紹介します。各企業の個別紹介記事も紹介しているため、そちらも併せてご覧ください。
紹介する企業は以下の4社です。
- シンクサイト株式会社 (ThinkCyte) – 再生医療のための革新的な細胞解析技術を開発(東京大学発)
- Symbiobe株式会社 – 光合成微生物で「空気」を資源に変える環境系スタートアップ(京都大学発)
- RadioNano Therapeutics株式会社 – BNCT×ナノテクノロジーで新しいがん治療法を研究開発(京都大学発)
- 株式会社Yanekara – EVと再生可能エネルギーを活用したエネルギーマネジメント事業(東京大学発)
ゴーストサイトメトリー技術で再生医療に革命「シンクサイト」

シンクサイト株式会社(以下、シンクサイト)は東京大学発のスタートアップで、再生医療分野の課題解決に挑んでいます。、独自の画像ベース細胞解析・選別技術「ゴーストサイトメトリー」を開発し、細胞の形態や動きを高速カメラとAIで捉えてラベル不要で細胞を識別・選別する装置「VisionSort」を提供しています。
解決する課題
再生医療や創薬分野では、高精度かつ効率的な細胞の選別が必要不可欠です。従来の技術では染色が必要だったり、スループットが低かったりといった課題がありました。ThinkCyteの技術はこれを解決し、医療の効率化と低コスト化に貢献しています。
大学発ならではの特徴
東京大学の研究室から生まれた先進的な技術で、基礎研究レベルの発想と実用化レベルのエンジニアリングが融合しています。学術的知見と機械学習・光学技術の連携による独自性が際立っています。
またシンクサイトはこれまでに累計約110億円もの資金を調達しており、世界的にも注目度を増すスタートアップと言えるでしょう。最先端の細胞解析技術で再生医療の実用化に貢献するシンクサイトの動向から、今後も目が離せません。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
光合成細菌で空気を資源化する京大発ベンチャー「Symbiobe」

Symbiobe株式会社(以下、Symbiobe)は、京都大学発のスタートアップで、地球温暖化や資源不足といった環境問題にユニークなアプローチで取り組んでいます。海洋性紅色光合成細菌を利用したバイオリソース事業を展開しており、この微生物を大量に培養することで二酸化炭素を固定し、肥料や飼料、繊維素材などの資源として有効活用することが可能です。
解決する課題
地球温暖化や窒素資源の枯渇といった環境問題に対し、光合成によってCO2を吸収し、有用物質に変換するアプローチで挑んでいます。また再生可能で持続可能な生産システムを提供しています。
大学発ならではの特徴
Symbiobeの強みは、大学発のディープテック企業ならではの研究開発力です。京都大学桂キャンパスに設置した大規模デモプラント(写真参考)で紅色光合成細菌の大量培養に取り組んでおり、これは世界最大級の規模だといいます。この培養ノウハウの蓄積に加え、目的に応じた細菌株の選抜・ライブラリ化も進めており、競合他社に先駆けた独自の技術基盤を築いています。
現在は山口県に大規模な実証プラントを建設し、本格的な商業化に向けた準備を進行中です。Symbiobeは学術研究の成果を環境ビジネスへと転換した好例であり、「空気の資源化」というビジョンが持つポテンシャルに国内外から期待が寄せられています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
BNCTとナノテクによる新しいがん治療開発「RadioNanoTherapeutics」

(引用:PRTIMES)
「がん治療に確かな光を。」を掲げるRadioNano Therapeutics株式会社(以下、RadioNano Therapeutics)は、京都大学発のスタートアップとして最先端のがん治療法を研究開発しています。同社は、ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)とナノテクノロジーの2つの技術を独自に組み合わせることで、革新的ながん放射線治療の実現を目指しています。
解決する課題
がん治療において、従来はホウ素取り込み効率が課題でした。同社の製剤はその課題を克服し、より高い治療効果を可能にします。BNCTの利点をナノテクノロジーで強化し、課題点を克服したこの新治療法は、次世代の放射線治療として将来的にがん治療の第一選択肢になり得るものだと期待されています。患者への負担軽減や従来治療で難しかった難治性がんへの適用可能性など、そのインパクトは計り知れません。
大学発ならではの特徴
RadioNano Therapeuticsが開発した新治療法は、京都大学での放射線治療とナノ材料研究の融合により生まれた技術です。医療と工学、化学が連携した高度な基礎研究をビジネス化しています。
事業面でも着実に成果を上げており、2024年にはシリーズAで累計約6億円の資金調達を完了しました。開発中のRN-501の臨床試験推進に向けて資金が投じられ、実用化に向けたステップを踏んでいます。大学の最先端研究から生まれたRadioNano Therapeuticsの挑戦は、がんに苦しむ患者と家族に新たな光をもたらす可能性を秘めており、医療業界や投資家から大きな注目を集めています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
EVと再エネをつなぐ次世代エネルギーマネジメント「株式会社Yanekara」

株式会社Yanekara(以下、ヤネカラ)は、東京大学発のディープテックスタートアップで、エネルギー分野のデジタルソリューションを提供しています。社名の「ヤネカラ」が示すとおり、「屋根から」得られる再生可能エネルギーの活用をキーワードに、脱炭素社会の実現に向けた技術開発を行っており、再生可能エネルギーの最適利用を目的としたクラウド型エネルギーマネジメントシステム「YanePort」やEV充電制御機器「YaneCube」などを開発しました。
解決する課題
ヤネカラの事業は家庭や企業における電力コスト削減とCO2排出抑制を同時に実現します。また、電力市場に連動したスマートな蓄電・放電制御で、再エネの導入障壁を下げています。
大学発ならではの特徴
東大の知見を活かしたデジタル制御やIoT技術の活用がヤネカラの強みです。さらに学内支援制度を活用して事業化し、大手企業との実証も積極的に行っています。
設立は2020年と比較的新しい会社ですが、東京大学の支援プログラムや大手企業との提携を通じて着実に事業を拡大しています。シード期から東京大学協創プラットフォームやVCファンドの出資を受け、実証実験では三井不動産と共同でスマートシティでのEV充放電プロジェクトを行うなど、産学連携・産産連携による実績も積み上げています。エネルギー×モビリティ×ICTを融合したYanekaraの取り組みは、日本のみならず世界的な課題である再エネ活用と電力マネジメントの最適化に対し、一石を投じる存在となっています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
まとめ:大学発スタートアップが拓く未来に注目
大学発スタートアップは、大学での研究成果を社会に実装するための重要なチャネルとなっています。今回紹介した4社はいずれも、独自技術で明確な社会課題に挑むと同時に、学術的なバックボーンを活かした強い競争力を持っています。今後も大学発の技術シーズが、産業界や生活者にとって革新的な価値を提供することが期待されます。
New Venture Voiceでは、このような注目スタートアップを多数紹介しています。
国内外の面白い企業についてもまとめているため、関連記事もご覧ください。







